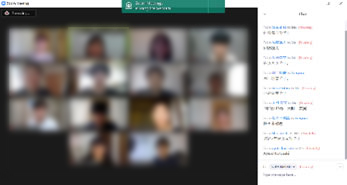授業事例
リアルタイム型 × 講義、語学留学生・国際連携科目 東南アジア理解講座(タイの言語と文化)
ウィライラック・タンシリトンチャイ 先生
授業概要・オンラインの活用状況
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
リアルタイム
| 講義の特色 |
|
|---|---|
| 開講期間 | 2019・2020年度春学期 |
| 配当年次 | 1~4年生春 |
| 開講地区 | 和泉キャンパス |
| 履修人数 | 11 |
| 使用言語 | 日本語 |
| 到達目標 | この授業履修による到達目標は、日本とアジアの架け橋たる実務型リーダーとして将来活躍することを目指し、特にタイの言語、文化、社会について基礎的理解を身に付けるとともに、タイ語会話の基礎やタイの文化・社会に基づくコミュニケーション方法の基本や知識を習得することとする。 |
| オンライン授業としての特長 |
|
オンラインを活用した授業方法・内容
リアルタイム形式
| 使用ツール | 2019年度までは接続ツールとしてパソコンを接続したPolycomを使って、パワーポイントやYoutubeなど資料や動画の紹介をしながら、授業を進めていた。2020年度はZoomを使って授業を実施し、チャット機能や録画機能を活用している。また、Commons-Iによる音声資料作成もできるようになった。授業時間外はメールとOh-o!Meijiを使って学生とコミュニケーションをとっている。 |
|---|---|
| ツール活用方法 | Polycom利用の際はパソコンを接続し、パワーポイントやYoutubeなどの資料提示や動画紹介の画面と講師の画面を切り替えて授業を進めていた。2020年にZoomを使いはじめて、Zoomのチャット機能で出席をとったり、質問を受けたり、クイズを行ったりしているほか、オンデマンドで復習できるように録画機能で授業動画を作成、提供している。また、パワーポイントやYoutube以外にもCommons-Iによる音声資料を作成、提供している。 |
| 内容 | 事前に学生に授業資料を送付し、全体の内容を把握してもらい、授業の際に発音、語彙、表現から導入してそれぞれの表現が表すタイ文化、タイ社会、タイ人の考え方、その背景などを説明する。その後、一人やペアで口頭練習やドリルを行い、練習済みの表現を使って応用的に会話をしてもらうことで学生の理解や語学力を確認する。タイ文化、タイ人の生活に関する動画も紹介し、日本の事情と比較して類似点、相違点を考えながらディスカッションを行ってさらに理解を深めてもらうようにする。 2020年度からZoomによる授業となったが、基本的に上記の授業内容や進め方で実施している。しかし、学生が同じ教室にいなく、TAのサポートや学生同士の助け合いがないということで練習用のパワーポイント、音声資料、動画、総まとめ用の資料、クイズ解答例など理解を助けるための資料を多く用意するとともに、いつでも復習できるように録画した授業のURLを学生に送るようにしている。 |
予復習の指示、成績評価の方法
| 予習 | 最低3日前までに学生に授業資料(その週と次週の資料)を送って、学生に事前に資料に目を通しておくと指示をしている。そして、毎回授業の最後に次回の資料を使って次回勉強する語彙や発音を紹介しておく。そうすることで、学生が事前に次回の内容を把握できるし、次回までにもう一度自分で予習できるため、スムーズかつ効率よく授業を進めることができる。 2020年度からは事前に会話練習用のパワーポイント資料(音声つき)および音声ファイルも追加して授業に来る前に予習してもらうように指示している。 |
|---|---|
| 復習 | 授業終了後、語彙・表現の整理表に勉強した語彙や表現を復習して整理するように指示している。また、語学力確認用の問題(問答形式)に回答してもらうとともに、文化や社会への理解を高めるため、学習したタイ文化や社会に関する課題も出して学生に自分の分野(政治経済、経営、文学など)の観点や知識を活かして論述してもらうことにしている。また、次回授業の冒頭で前回学習したことを復習したり、質問・疑問に答えたりしてから、授業を進めるようにしている。 2020年度からは上記のことに加えて、授業の冒頭でZoomのチャット機能を使って復習のためのクイズ実施もしている。また、理解を助けるための重要文型をまとめた資料も配布して再復習してもらうようにしている。 |
| 成績評価 | 2019年度 ・平常点 20% (クラス活動 10%、勉学態度 5%、表現力 5%) ・課題 20% ・中間テスト 25% ・定期試験 35% 2020年度 ・平常点 20% (クラス活動 10%、勉学態度 5%、表現力 5%) ・課題 20% ・中間テストの代替レポート 25% ・期末テストの代替レポート 35% 課題やレポートは自分の学びを振り返り理解を深められるように必ずコメントをつけて学生へフィードバックする。 |
学生とのコミュニケーション
| 学生とのコミュニケーション方法 | メールによる連絡:2019年度は場合により、国際教育事務室の協力を得て学生に重要連絡をすることもあった。 2020年度はメールと合わせてZoomやOh-o!Meijiも使って学生とコミュニケーションをとるようにしている。 |
|---|
工夫や苦労したこと
| 工夫した点 | タイの言語と文化に関して知識や経験がない学生が多く、分からない点、質問などがあれば、遠慮せずに質問してもらうなど学生全員の理解を確認してから授業を進めるようにしている。 タイのみならず、アセアンや日本の事情とも比較して理解を深めるようにしている。 画面を通した授業は学生の表情が分かりにくい場合があるが、学生の理解を確認するため、「分かりましたか、分からない部分がありませんか」との先生の問に対して必ず声を出して返事してもらうようにしている。 オンライン授業や遠隔授業は音声がはっきり伝わらない時があるため、ゆっくり話をするようにしている。 見やすい、分かりやすい資料および総まとめ用の資料を用意する。 課題・宿題を添削する時に、学生の理解を助けるため、必ず詳しい説明やコメントを加えておく。 学生参加型の授業として語学関係の練習だけでなく、実際のタイの社会、文化、言語、タイ人の行動などを理解してもらうため、ニュース、映画、最近の話題などの動画を紹介してディスカッションも行うようにしている。 学生がいつでも復習できるように録画した授業のURLを送るようにしている。 授業後、質問があった場合、メールで質問を受けつけて回答するようにしている。 |
|---|---|
| 苦労した点 | 画面を通した授業であるため、疑問があったりするときの学生の表情や学生の発音を確認することが難しい場合がある。 課題・宿題の添削した部分は学生が正しく理解しているかどうか入念にフォローや確認する必要がある。 対面授業より学生とのインタラクティブなコミュニケーションをとることが難しい場合がある。 |
| 失敗した点 | Polycomによる授業実施の場合は画面が止まったりする時があった。一方、Zoomによる授業実施は複数のID、パスワード、配信時間など設定ができるため、注意しないと、学生に違うID、パスワードを知らせてしまうおそれがある。 |
| アイデア | 海外と接続し実施する授業の場合、タイムゾーンや時間差などに注意し時限を設定する必要がある。 各回に分かりやすい資料を提供するだけでなく、学生の理解を助けるため、総まとめ用の資料も必要である。 オンライン授業は学生が受け身的という雰囲気があるが、学生参加型のインタラクティブな授業にするため、動画など学生の興味を引く教材を使って適度に学生とのディスカッションやプレゼンテーションも取り入れる必要がある。 |
| 改善した点 | 2019年度の授業はPolycomによる遠隔授業であり、同じ教室に集まった学生に対して授業を実施していた。時折画面が止まったりすることがあったが、それ以外のシステム的な問題はなかった。学生が同じ教室にいるため、グループワーク、学生同士での協力・助け合い、TAによりサポートがすぐできた。しかし、就職活動やその他の用事で教室に来れなかったりすると、授業を欠席せざるを得ないという問題があった。 一方、2020年度はZoomによるオンライン授業になり、Polycomによる授業実施よりシステム的に安定しているため、授業運営はスムーズに行うことができた。また、チャット機能、録画機能などZoomの様々な機能を使って学生出席の記録、小クイズの実施、学生とのコミュニケーションも簡単に取れて効果的である。学生にとって、Zoomはパソコンをもってどこからでも授業に参加できるため、就職活動中でも授業を欠席しなくていいし、録画した授業の動画もあるため、いつでも復習できるというメリットがある。実際の例として就職活動中の学生で、Zoomによるオンライン授業のおかげで企業訪問前や訪問後に外から授業に参加する人がいた。また、Zoomによる授業の場合は自宅などの自分のスペースで授業に参加しているため、他の学生への遠慮がいらず自由に発音したり練習したりすることができるとの学生のコメントもあった。 |
授業に関連のある画像