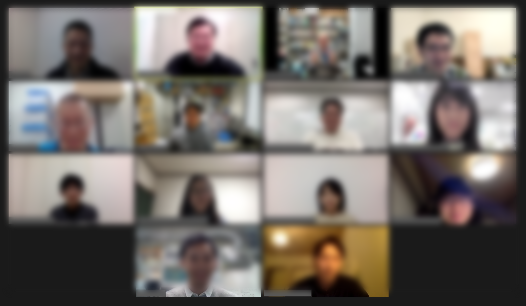授業事例
リアルタイム/オンデマンド併用型 × 演習大学院研究科間共通科目 融合共創プロジェクト
萩原 健太 先生
授業概要・オンラインの活用状況
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
リアルタイム
オンデマンド
| 講義の特色 |
|
|---|---|
| 開講期間 | 2020年度秋学期 |
| 配当年次 | 大学院博士前期・後期課程 |
| 開講地区 | 駿河台キャンパス |
| 履修人数 | 14 |
| 使用言語 | 日本語 |
| 到達目標 | 本講義の到達目標は、異なる研究科間の大学院生の研究交流を通して「異分野融合のための足掛かり」を構築することである。 |
| オンライン授業としての特長 |
|
オンラインを活用した授業方法・内容
リアルタイム形式
| 使用ツール | Zoom、パワーポイント、Oh-o!Meiji |
|---|---|
| ツール活用方法 | Zoom:グループワーク、プレゼンテーション、講義での接続ツール パワーポイント:プレゼンテーション資料の作成ツール Oh-o!Meiji:Zoomアドレス等の連絡ツール |
| 内容 | まず、各受講者による自分の研究内容についてプレゼンテーションを行った。ついで、グルーピングを行い、融合共創プロジェクトチームをつくり、グループワークにより各自の専門を融合することで、どのような社会貢献(災害や食糧問題、気候変動などに対する対策)ができるのかを議論した。最後に、グループワークの結果をプレゼンテーションした。 |
オンデマンド形式
| 作成ツール | パワーポイント、Oh-o!Meiji |
|---|---|
| 動画の平均時間 | パワーポイント:講義資料の制作ツール Oh-o!Meiji:資料の配布ツール |
| 内容 | 第3回以降の実習(グループワーク及びプレゼンテーション)について説明を行い、融合共創研究及びSDGsに関する講義を通して、最終プレゼンテーションである融合共創研究のリサーチプロポーザルへ向けた取り組みを指導した。また、次回までの課題として自身の研究内容のプレゼンテーション資料をOh-o!Meijiへ提出するよう指示した。 |
予復習の指示、成績評価の方法
| 予習 | 融合共創研究事例を学習した上で、自身の研究・研究分野でどのような融合的研究事例があるか、または可能であるか考えてくるよう指示した。 |
|---|---|
| 復習 | 最終プレゼンテーションまでの取組みや教員からのフィードバックを今後の自身の研究活動に取り組むよう指示した。 |
| 成績評価 | 提出課題、プレゼンテーション内容、受講姿勢から総合的に評価 |
学生とのコミュニケーション
| 学生とのコミュニケーション方法 | Oh-o!Meiji内アンケート機能 Zoom |
|---|
工夫や苦労したこと
| 工夫した点 | Zoomによるグループワーク及びプレゼンテーションを円滑にするため、ウェブ用マイクとカメラを支給した。 研究分野の異なる学生(3~4名)で班を構成するよう調整した。 一班に一人以上の教員を常に配置し、グループワークの進行具合を把握するとともに助言を与え、期限を超過することなくプレゼンテーションまで行えた。 グループワークの作業中に、他研究分野の教員に意見を求める時間や参加教員による融合共創研究に関する事例紹介の時間を設け、リサーチプロポーザル発表に向けた指導を行った。 事前に融合教育プログラムに参加している本学および他大学(広島大学・山梨大学)の教員にメールにて参加協力を求め、多くの教員にZoomによる最終プレゼンテーションへ参加してもらうことができた。 参加した教員からの学生へのフィードバックとして講評コメントを収集し電子ファイルとして配布した。 |
|---|---|
| 苦労した点 | 今年度が初回かつ複数の教員による授業であったため、内容や構成について長時間の打ち合わせが必要であった。 合宿形式からZoomでの開催に変更になったため、当初の計画から大幅な変更が必要であった。 学生への支給品の配送で個人情報が必要な場合があった。 連絡や資料配布はOh-o!Meiji上で行っていたが、通知をメールに転送設定していない学生もおり、何件か教員経由で連絡をとる必要があった。 |
| 失敗した点 | Zoomのブレイクアウトルームを用いて班別のグループワークを行ったため、他班の話し合いの様子や進行具合を他の受講生が確認することができなかった。 プレゼンテーション時を除き、他班の受講生とコミュニケーションをとる時間があまりなかった。 Zoomでなく合宿形式で受講したかったという意見もあった。 今年度からの授業であったため、受講者の研究分野に少し偏りが見られた。 |
授業に関連のある画像